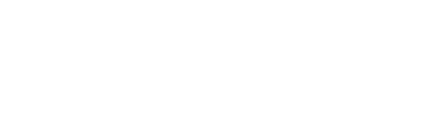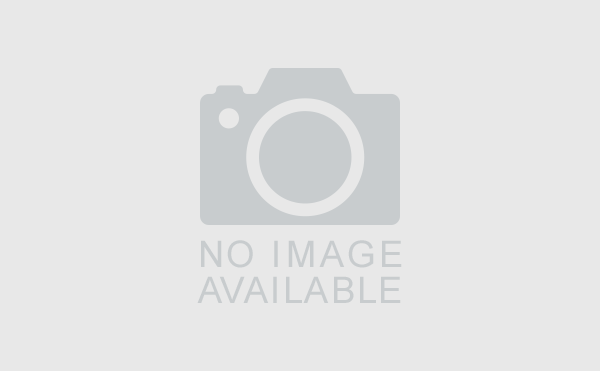こんにちは。暑いですね。
川平屋の齋藤です。
着物業界に入って5年になりますが、新入社員の時に
羅(ら)?!紗(しゃ)?!絽(ろ)?!と名前も個性も魅力的な夏の生地に不思議な感動を覚えたものです。
今回はそんな夏にもってこいの素材の紹介をしていきますね!
羅・紗・絽って何が違うの?
①【羅とは?】
②【紗とは?】
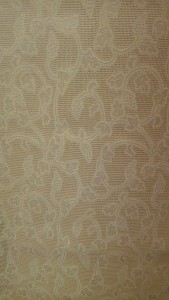
薄く透き通る絹織物で、カジュアルからフォーマルまで広く使われてます。
織り柄のある紋紗(もんしゃ)、紬糸で作られた紗もありますね。
長襦袢を重ねた時の透け感は、涼しげです。
ぼんやりとした様を示す『紗がかかったような』という表現はなるほどですね。
③【絽とは?】

紗の変形にあたり、7・5・3本おきに緯糸に2本の経糸を交差させて織っていくもので、それぞれ七本絽・五本絽・三本絽と呼ぶそうです。
私が初めて見たものは、夏喪服です。
フォーマルの席にふさわしく訪問着、小紋、色無地など、最近はめったに見られませんが、黒留め、振袖などもあります。
昔の暮らしの中で考えて作り出された夏の生地に、不思議な魅力を感じませんか?
きものでわからないことは、お気軽に川平屋にお問い合わせ下さいね。
↓来店予約はこちらから↓
↓お問合せはこちらから↓
https://kawahiraya.co.jp/contact/
〒471-0023
川平屋豊田店(和ギャラリー川平屋)
愛知県豊田市挙母町1-43【専用駐車場15台分完備】
TEL (0565)32-0201
E-mail:wagallery@kawahiraya.com
HP:http://www.kawahiraya.co.jp/
営業時間:10:00~19:00
定休日:火曜日・月末水曜日